先日、娘たちの学校で「文化芸術会」なるものがありました
オイラが中高生の頃には無かった(ウチの学校だけ?)イベントなのですが、
テーマに沿って教室を飾ったり、演劇を発表したり、
オリジナルの動画を制作し発表したりするものです
もちろん、企画、制作、演出など、全てを生徒たちが行うものです
上の娘が入学した年が、まさにcovid-19真っ盛りの頃だったのですが、
時差登校や、短縮授業などの影響もあり、
思ったような生徒間のコミュニケーションが取れない中、
素晴らしい発表をオンラインで見せてもらって感動したものです
その後何年間はオンライン配信オンリーだったのですが、
今年から、再び学校内での発表となりました
外部からは保護者と、一部の招待者のみという縛りはあったものの、
当日の会場は、生徒たちを含めて、非常に盛り上がっていたそうです
(カミさん談)
さて、その文芸会でのウチの娘たちですが、
なんと、各クラスでの出番のほかに、ステージに立ちました
このステージ、自由見学ではなく、全校生徒が一斉に集まっての鑑賞となります
そして、その内容ですが・・・
軽音でのバンド演奏w
全く揃いも揃って誰に似たんだか(苦笑
下の娘はベース担当
キャリアは軽音に入ってからやり始めたので、まだ半年未満ですね
顧問の先生の勧めもあって、披露したのはこちら
全員1年生のガールズバンドなんですけど、その実力がすごい!
演奏後の会場のMCで、
「メンバー全員が、軽音に入ってから楽器を始めた1年生で・・・」
と話すと、会場がざわつくざわつくw
「え?1年・・・
「え?5月から始めた・・・
「マジかよ・・・
いや本当に立派だったよ
実は、次の出番を控えて、ステージ袖で待機していた上の娘も、
その成長ぶりに涙を流していたとか(うんうんわかるよ)
そして、その上の娘はドラム担当
軽音に入ってからやり始めたので、実質2年くらいかな?
2年生、3年生、4年生の学年を超えた編成にて、こちらを披露しました
さすが軽音内で一番キャリアのあるバンドだけあって、安定しているステージングで、見てるこっちも安心です
練習の時にガチガチだった新人の2年生の子も、
演奏後には笑顔が出ててよかったですよ
実際の動画は、いろいろな都合によりSNSなどへのUPができないので、
どうしてもという方は直接オイラに連絡ください(笑
と、前振りが長かったのですが、そろそろ本題へ
この文芸会が終わった翌日、
顧問の先生が撮影してくれた動画や、
カミさんの撮ってきてくれた動画などをゆっくり見てたんですけど
ふと気づくと、娘たちの姿が見えない
さらには、オイラのギターや、オタマトーン、
下の娘が文芸会で使っていたベース、
カミさんのエアロフォンも一緒に姿を消していました
ドコに行ったのかなと思ってたら、別室から何やら音が聞こえてくるんですよね
自宅にはいくつか部屋があるのですが、
そのうちの一つに、通称「わくわく部屋」と呼んでる、
みんなが好きなこと出来て、楽しむ用の、共有スペースのような部屋があります
そこから音が聞こえてくるんです
そうです
今まではベースしか触ってこなかった下の娘がギターを手に取ってるし、
上の娘はオタマトーンとエアロフォンを弾いてるんです
ウチある楽譜を広げながら、
新しい楽器に挑戦しているんです
もう、カミさんとオイラはニヨニヨですよw
まさにこういう用途に使って欲しかった「わくわく部屋」なんです
今までは、カミさんのシステム「M1MBA + スタジオディスプレイ」で動画編集をしたり、
プロジェクターでお気に入りの動画を見たり、
オイラの「UR22C + MBA」に接続したマイクでカラオケを楽しんだりしていましたが、
こういうふうに使ってくれるのもいいですよね
となると、オイラも大人しくしてはいられません
いつぞやの「わくわくエンジン」にて「スーパーパパ」を目指していると公言した者ですので、
娘たちに遅れをとるわけにはいかぬ!
しかし、何を始めようとふと考えた時に、
具体的な「コレ」というものがなかったんですよね
そんな時に、こんな記事を見つけました
インスタコード
初めて聞きました
(ちな、カミさんもこの名前を最近知ったらしい)
この記事だけでは、どんなものかがよくわからなかったので、
実際に公式を確認に行きます
ふむふむ・・・
なるほどなるほど
なかなか面白そうな仕組みだなぁ
と、ここで何度か出てくるある言葉に目が止まります
度数(ディグリー)
KANTAN Music
気になるものは調べてみる性格なので、
google先生の力を借りながら、とある方のブログに辿り着きました
んで、リンク先を参照しながら、読み漁っていた時のことです
あれ
オイラこれ知ってるわ
ヒロえもんのことを知っている方なら、
オイラが音楽学校には行ってないことはご存知のことでしょう
また、ついでに言えば、楽器関係は、ほぼほぼ独学ということもご存知でしょう
ですが、たった一つだけ例外があり、教室というスタイルで学んだ経験があります
幼稚園から小学校6年生まで通っていたヤマハの音楽教室です
現在のヤマハのカリキュラムでいうところの
幼児科 → ジュニアエレクトーンコース(小学5年でジュニアピアノコースへ変更)
というコースに通っていました
これの、幼児科の課程の頃の記憶です
当時使用していたテキスト(ぷらいまりってヤツでした)に、たくさんの曲が譜面付きで載っていて、
先生の伴奏に合わせて歌ったり、打楽器を打ったり、
電子ピアノを弾いたりするレッスンスタイルでした
そのレッスンの時です
新しい曲に進む時に、先生は必ずこう言うのです
ではこれから先生が言う場所(譜面上)に書いていきますよー
はい、ここが「いち(I)度」
それでここが「よん(Ⅳ)度」
そしてここが「ぞくしち」
さいごは「いち(Ⅰ)度」にもどりまーす
素直な子供だった当時のオイラは、先生の言われる通りに譜面に書き込んでゆきます
Ⅰ度、Ⅳ度
そうそう「ぞくしち」の書き方ですが、こうに書くんだよーって習いました
Ⅴ7
カンの良い方は、もう気づいていることでしょう
そして、先生の伴奏に合わせて歌を歌うその後に、こういうのもありました
はーい、今度は和音で歌いますよー
ドミソー
ドファラー
シファソー
ドミソー
の順番ですよー
当時の素直なオイラは、先生の言う通りに歌っていました
その後、中学は自宅から通えない距離の学校へ進学したので、
ヤマハ音楽教室もそこで途絶えてしまいました
その代わりと言ってはなんですが、中学から入った寮にて、他の楽器に出会います
ちょうど「イカ天」の時代です
通っていた中高の先輩に、某有名ギタリストがいたということもあったのかなかったのか、
順調にオイラもギター、ベースと進んでゆきます
しかし鍵盤を弾けるというスキルは当時大変貴重だったため、そっちでの出番が多かったですね
そして、高校になった頃は、
オイラなんかよりもっとすごい鍵盤テクニックを持っているイケメンが入ってきたので、
オイラの出番はギター、ベースへと再び戻ってきました
この頃、学校で流行っていたのはロカビリーでしたが、
自分自身は洋楽、特にメタル系にハマっている頃でして、
メタリカ、アンスラックス、ジューダスプリーストなどを
邦楽では、ちょうどXのBLUE BLOODが出た頃でして、
YOSHIKIの信者(大笑)にもなってました
もちろん、ギターの練習もしてました
当時はひたすらTAB譜を見ながらのコピーだったのが懐かしいなぁ
今思えば、そのころに出会っていたんですよね
ギターコードの「セブンス」、「sus4」、「add9th」というお約束のアイツらです
仲間内にはジェフ・ベックやエリック・クラプトンといった系統が好きな奴もいて、
そういう奴らが、
「ペンタトニックがさぁ・・・」
「スケールがさぁ・・・」
なんてことを言ってたのを思い出します
やや話が脱線してきたので無理やり戻すと、
先ほど紹介したブログの記事の中でこんなページがありまして
そこで気づいたんですよ
(というか、なんとなく思ってたことがピッタリはまったんですよ)
あぁ
これ「いちど → よんど → ぞくしち → いちど」のことだ
ダイアトニックとか度数(ディグリー)なんて難しく聞こえるけど、
幼稚園の頃にやってたアレだ
7度、9度を足すからセブンス、add9thなんだ
てことは・・・だよ
ヤマハの音楽教室って、幼児科の頃から、この基礎理論を徹底的に叩き込むように作られてるんだ
度数表記させるのも
和音で歌わせるのも(もちろん、当時はドを基準になるように展開している)
「トニック → サブドミナント → ドミナント → トニック」というファンクション構造も
セブンスコードも
なんだよ
幼稚園の頃にみんなやってるじゃん
すげー
ヤマハ
すげー
最後にヤマハで〆るので、お約束のアレをw

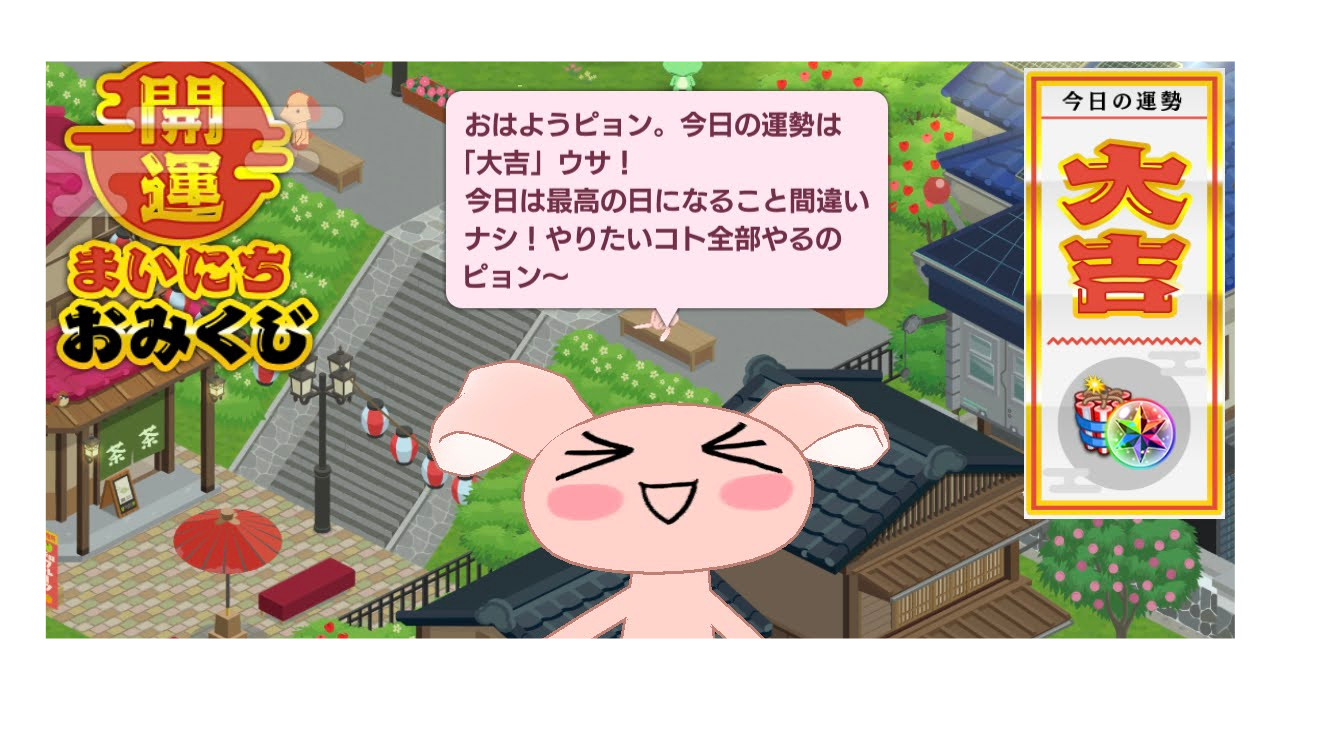





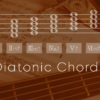


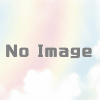
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません